子どもの教育資金の準備と言えば、まっさきに連想されるのが学資保険です。
しかし、学資保険以外でも教育資金を積み立てられる保険があります。
最近、学資保険の代わりによく活用されているのが、低解約返戻金型終身保険です。
この低解約返戻金型終身保険は、学資保険の代わりとしてとても人気がありおすすめです。
学資保険はどんな保険?

学資保険は、子どもの教育資金を準備するための貯蓄型の保険です。
子どもが小さいうちから毎月保険料を支払い、大学進学時期に教育資金として満期保険金を受け取ることができます。
学資保険にも様々な種類があり、大学進学時期だけでなく小・中・高の進学時や大学在学中にも祝い金を受け取れるプランなどもあります。
契約者が亡くなった場合は、それ以降の保険料の支払いが免除されるのが一般的です。
教育にはお金がかかるので、学資保険は計画的に教育資金を積み立てるのに有効な保険です。
低解約返戻金型終身保険とは
低解約返戻金型終身保険とは、保険料払込期間中の解約返戻金を低く抑えることで保険料を安くした一生涯の死亡保険のことです。
保険料払込期間中の解約返戻金は低く抑えられていますが、保険料払込満了後の解約返戻金は大きく増加し、これまでに支払った保険料以上の解約返戻金を受け取れるプランもあります。
教育資金準備のための保険ではありませんが、この特徴を活用して学資保険の代わりに契約する人が多くいます。
学資保険の代わりに低解約返戻金型終身保険がおすすめの理由

教育資金を学資保険で準備するよりも、代わりに低解約返戻金型終身保険で準備した方がおすすめの理由がいくつかあります。
被保険者が亡くなったときに受け取る金額が大きい
学資保険は契約者が亡くなったときに、それ以降の保険料の支払いが免除されますが、低解約返戻金型終身保険だと被保険者が亡くなったときに死亡保険金を受け取ることができます。
低解約返戻金型終身保険の保険金は、教育資金として将来受け取る予定だった解約返戻金型よりも金額が大きく設定されているため、学資保険よりも有利です。
学資保険よりも自由度が高い
学資保険の保険期間は、子どもが18歳~22歳になるくらいまでで、満期保険金を受け取ることで終了します。
それに対して、低解約返戻金型終身保険の保険期間は終身です。
子どもが進学をしなかったり、預貯金で教育費を十分まかなえたりしたときには、低解約返戻金型終身保険を解約せずに保障を継続することも可能です。
解約や継続以外にも、一部のみを解約(減額)することで、解約返戻金の一部を受け取ることもできます。
低解約返戻金型終身保険は、その時の経済状況に応じた選択ができるため、学資保険よりも自由度の高い保険です。
据え置くと返戻率上がっていく
低解約返戻金型終身保険の返礼率は、解約しないで据え置くことでどんどん上がっていき、受け取れる解約返戻金も増えていきます。
子どもの教育費として解約する必要がなくなれば、据え置くことで当初の予定よりも増えた解約返戻金を老後資金に回すこともできます。
子どもの年齢に関係なく加入できる
学資保険に加入できるのは、子どもの年齢が6歳くらいまでです。
一方の低解約返戻金型終身保険は、子どもの年齢に関係なく加入できます。
子どもが大きくなってからでは学資保険には入れませんが、低解約返戻金型終身保険なら検討の余地があります。
学資保険の代わりに低解約返戻金型終身保険に入る場合の注意点

学資保険の代わりに低解約返戻金型終身保険を活用するのはおすすめですが、注意しなければならない点もあります。
保険料払込期間中の解約返戻金は少ない
低解約返戻金型終身保険は、そのネーミングにもあるように保険料払込期間中は解約返戻金が低く抑えられています。
保険料払込期間中の解約返礼率は、一般的な終身保険の70%ほどです。
保険料払込満了前に解約すると、大きく元本割れしてしまいます。
保険料払込期間中に解約する可能性があるのなら、低解約返戻金型終身保険はおすすめできません。
契約内容によっては保険期間満了後も元本割れの可能性がある
契約年齢が高かったり、契約年数があまり経っていなかったりすると、保険料払込満了後でも返礼率が100%を下回る(元本割れ)可能性があります。
教育資金目的で加入するのであれば、解約予定時の返礼率はどれくらいになっているのかをチェックしておくことが重要です。
学資保険か低解約返戻金型終身保険で迷ったら保険のプロに相談

教育資金を生命保険で準備するのなら、個人的には学資保険よりも低解約返戻金型終身保険の方が、メリットが多くておすすめです。
とはいえ、すべての人にとって低解約返戻金型終身保険の方がいいわけではありません。
どちらにもメリットとデメリットが存在します。
学資保険と低解約返戻金型終身保険で迷ったときには、保険のプロに相談してアドバイスをもらうといいでしょう。
複数の保険会社を扱っている人であれば、複数の保険商品の中からベストなプランを提案してもらうこともできます。




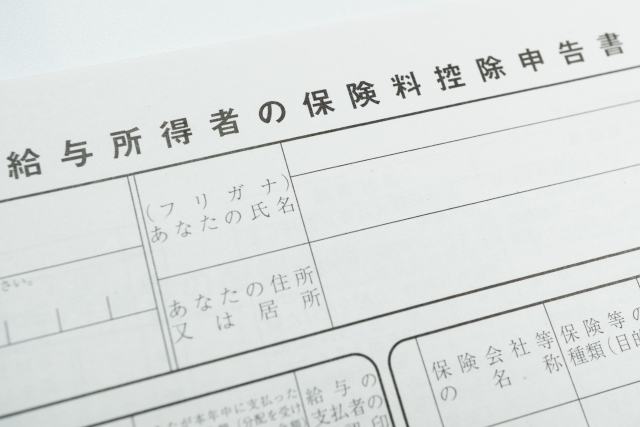
コメント